はじめに
今回はシンセサイザーの選び方についてまとめます。
正直、こだわりが無ければ無料のSynth1で大丈夫です。
これをDLして使い方を覚えてください。(無料ですが、十分良い音が出ます。
ここから先は、よりこだわっていきたい人向けに解説していきます。
シンセサイザーの種類分け
まず、シンセを選ぶ際に重要になる区分についてまとめます。
ハード / ソフトシンセ
ハードシンセ = リアルにモノがあるモノです。
ソフトシンセ = モノは存在しなく、PCのソフトとして動くシンセサイザーです。
ハードシンセは普通に5万~50万ぐらい飛びます。
ソフトは高くて~3万。
ただ、ハードの方が音の厚みが強いなどの理由でコアな方はハードを使ってます。
(モニタリングヘッドフォン+オーディオインターフェースを持って無いと違いがわかりにくい)
MIDI入力可能のハードシンセであればDAW → PC → MIDI出力 → ハードシンセに音を送る。
そして、ハードシンセから出た音を録音して使う猛者も居ます。
ただMIDI対応しだしたのが1980年代~なので、ビンテージ系のハードシンセでは使えません。
・ハードシンセ = リアルに"モノ"がある
・ソフトシンセ = PC上で動く"ソフト"だけ
・ソフトシンセは安くて、かさばらず、扱いやすい。
・9割ぐらいの人はソフトシンセで十分
・音の揺らぎや厚みにこだわる猛者はハードを使う
・1980代以降のMIDI対応シンセでは、DAWの音を入力できるモノがある以上がハード / ソフトシンセの違いです。
普通のシンセ / セミモジュラー / モジュラーシンセ
普通のシンセは文字通り、普通のシンセサイザー。
内部配線済みで、ツマミやスライダーのような半固定、可変抵抗器以外の変化はできない。
セミモジュラーシンセも内部配線済み。
だが一部の処理を電線を使って刺す事で変化させることができます。
そして、モジュラーシンセは内部配線がされていないシンセ。
線を使って音が出る回路を1から作る必要があります。
そのぶん、自由度の高い音作りができる。
なので、コアなオタクの方が使ってます。
ユーロラック / 非ユーロラック
モジュラーシンセにはユーロラック形式とそうでないモノが有ります。
◆ユーロラック形式
「ユーロラック」と呼ばれる規格の土台に、任意のパーツを入れていく形が主流。
1990年代以降のモジュラーシンセは、ほとんどコレです。
ソフトのモジュラーシンセもだいたいユーロラック形式を再現してます。
◆非ユーロラック形式
1960年代の原始モジュラーシンセには、ユーロラックの概念がありません。
なので、パーツを組み変えれません。
(魔改造すればできない事もない)
過去の1960年代モジュラーシンセ再現ソフトには、
このようにパーツが固定されてるものがあるので注意。
・普通のシンセ = 内部配線済み、ツマミなどでしか操作できない
・セミモジュラー = 内部配線済みだが、一部の処理を外部の配線で変えれる
・モジュラー = 内部配線なし、1から音を出す処理を外部配線で作る
・ユーロラックモジュラー = モジュラーシンセに使用するパーツを自分で選ぶ形式
・基本普通のシンセでok、自由度やこだわる猛者はモジュラー系を使うことがある以上が普通のシンセ / セミモジュラー / モジュラーシンセの違いです。
モノフォニック / ポリフォニック
モノフォニック = 単音しか出せないシンセ(初期の頃のシンセ)
ポリフォニック = 和音が出せるシンセ(1970年代以降のシンセ)
今どきのシンセの大半はポリフォニックですが…
古いシンセや、その再現ソフトを買うとモノフォニックな事があるので注意。
↓モノフォニックのソフトシンセが売られてる例。
また、ポリフォニックシンセでもアルペジエーターやシーケンサー機能を使うと、モノ化します。
(C → E → G → Eのように音を順番に鳴らす機能)
買う時は、体験版などを入れて、和音が出せるか確認してください。
アナログ / デジタル
この区分は、古い感じの音、エモい感じの音を作りたい人は意識してください。
・アナログ = 音の出る回路を電子回路として作ったもの
・デジタル = 音の出る回路をデジタルで作ったもの
(シンセの中に小さなパソコンが入ってるイメージ)
デジタルとアナログの使い分けを意識することで、音の古さ具合を表現できます
・1970年代まではアナログシンセが主流
・1980年代以降からデジタルシンセが登場して流行るつまり、YMOっぽい音が欲しいならアナログ(Prophet-5再現系)
小室哲哉さんっぽい音が欲しいならデジタルを使うようなイメージ(JD-800再現系)

FM / PCM / アナログモデリング
この3つは、デジタルシンセの分類です。
・FM音源 = 金属っぽい音が得意(ある波形に高速でピッチを変える波形をぶつけて波の形を作る)
・PCM音源 = 今でいうサンプラー(録音した音を鳴らす)
・アナログモデリング = シンセサイザー内の小さなPCでアナログシンセの挙動を再現する
この3つも使い分けると音の古さを変えれます。
・FM音源 = 1980年代前期っぽい音になる
・PCM音源 = 1980年代後期っぽい音になる
・アナログモデリング = 1990年代っぽい音になる
シンセサイザーを選ぶ際の注意点
シンセサイザーを選ぶ際の注意点は下記。
・お金をかければいい音が出るわけではない
・同じ処理でも違う音が出る
・すべての音を表現できるわけではない
同じ処理でも違う音が出る
シンセサイザーは同じ処理でも違う音が出ます。
おなじ歌でも、別の人が歌うと違う曲になるような現象が起こります。
例えばこちら。
モジュラーシンセで3種類のモジュールを使って同じ処理を組んだ時の挙動比較。
やってる処理、パラメーターの値は同じです。
が、音が変わってます。
音楽業界のソフトは、同じ処理でも違う音が出ます。まず、この事だけ理解してください。
このような違いは、メーカー固有の偏りや、1つの機材特有の偏りとして現れてきます。
すべての音を表現できるわけではない
シンセを理解すれば、ドラムっぽい音まで作れる!
なら、「どんな音でも作れるのでは?!」と思うかもしれません。
が、実際にはそれはできません。
当たり前ですが、どんなモジュラーシンセを組んでも推しのVtuberの声は出ません。
楽器系の音も再現に限界があります。
だから、可愛い系の声を収録したサンプルパックなどが売られています。

また、先ほど紹介したメーカーや機材固有の音の違いも表現は難しいです。
なので、シンセで作れるのは、そのシンセから出る「シンセ系」の音だけです。
◆シンセ系の音
・現実に存在しない、演出目的の効果音(ゲームやパチンコ系の音)
・シンセリード
・シンセベース
・シンセPAD
・ドラム系の音(ノイズを良い感じ調整すると表現できる)
・ピコピコ系の音(矩形波)
・アルペジエーターやシークエンサーといった時間軸で音が変わる変化
…などすべての音を表現できるわけではない事に注意してください。
値段が高いシンセがいい音とは限らない
良い音を、皆さんが「頭の中で思い描いた音」と想定します。
人は無から何かを思い描く事はできません。
思い描くためには、過去に何かしら聞いた音があるはずです。

例えば、YMO、小室哲哉さん、といった懐かしい系の音。
もしくは今どきのFuture Bass、ハードコアの曲に使われる音。
この「思い描いた音」というのが重要です。
これで、何を選べばいいかという選択肢が変わってきます。
懐かしい、エモい、チルい系の曲を作るなら1960~1990年代の再現シンセが使えます。
が、今どきのダブステップ、トランス、ハードコアには合いにくいです。
(あえて使うのもアリですが…)
逆に今どきの曲を作るなら、最近出たソフトシンセがおすすめ。
懐かしい系のシンセはメインでは使いにくい可能性があります。なので、今どきの高額、高性能シンセを買って作れるのは今どきの音。
懐かしい系の音は作れません。
つまり…
値段が高い高性能シンセから、いい音が出るわけでない。
用途に合ったシンセを使う事で良い音が出る。
という事に注意。
シンセサイザーの選び方
注意点で下記の3つを紹介しました。
・同じ処理でも違う音が出る
・すべての音を表現できるわけではない
・値段が高いシンセがいい音とは限らないこの3つを考慮した上でシンセの選び方を解説します。
歴史を調べる
「思った通りの音」の出し方を考えます。
なにかを「思う」というのは、その元になった経験があるはずです。
その原体験が何なのかを掘り下げるのに「歴史を調べる」アプローチが有効。
【例】
・YMOの音楽に使われていたシンセサイザー音
・小室哲哉さん系の音楽に使われていた、1990年代J-POPの音
・今どきの音楽に使われてる音
…など。シンセ史の詳細はこちらでまとめました。
そして、思った音の由来を考えます。
そこから、シンセを選ぶことができます。
・YMOの音楽に使われていたシンセサイザー音 → 1970~1980年代のシンセ
・小室哲哉さん系の音楽に使われていた、1990年代J-POPの音 → 1990年代のシンセ
・今どきの音楽に使われてる音 → 最近出たシンセを使うYMOの音楽 → Prophet-5というシンセ → それの再現、Re-Pro5を使う。
90年代、小室哲哉さん系音楽 → JD-800 → 公式が再現したシンセがあるからそれを使う。

今どきの音楽 → 古い系のシンセを避けて、最近出たものを使う → SERUMなど。
このようなアプローチでシンセを選ぶと”思った通りの音”に近づきやすいです。
ただ、一口に「今どきのシンセ」と言っても色々あります。
そこで、師を見つけるアプローチをとります。
師を見つける
音楽は何が正解というものは無く、最後は”好み”で片づけられる世界です。
なので、迷うことが多々あります。
そこで… 師匠となる人、参考にする人を決めます。
理想は”憧れ”よりも、”日常”的に音楽を聴いていた人。
人生で触れた時間が長い人がおすすめ。

Nhatoさんみたいな曲にあこがれてSpire買いましたが…
人生で触れてる時間はYMOなどの方が長く、長年思った音が出ないと苦しんでました。
迷った時に、その人の歴史を調べれば指針なります。
◆今どきシンセ系をより細かく見る
・いろんなアーティストが使ってるのがSERUM
・Nhatoさん界隈、日本のTranceミュージックで系で使えるのがSpire。
…のように参考にする人を見つけると、シンセを選ぶ手がかりになります。
プリセットで考える
プリセット=シンセの設定を記録したモノ。
プリセットの多さも選ぶ上で重要な要素になります。
ユーザーが多いSERUMはやはりプリセットが多く便利
Spireにもプリセットがあります。
Nhatoさんのプリセットが有名。
ただ、総数はSERUMよりは少ない。
プリセットなので、特別新しい処理が増えてる訳ではないです。
なので、慣れると近い音を自作できますが…。
初心者で、今すぐに曲を作りたい方はプリセットで選ぶのも1つの手。
最後は顔(デザイン)の良さで決める
それでも迷ったら、使いたいデザインで決めます。
結局どんなに良くてもデザインが使いにくいと使わなくなります。
見た目の”好き”で選ぶのも有効なアプローチです。
おすすめシンセサイザー
どんな音を出したいかで、何を選ぶか変わります。
なので、正解はこちらに無いです。
それを分かった上で… おすすめできるシンセサイザーについてまとめます。
(最後は自分にとっての正解を見つけてください)
今どきのシンセ
今どきシンセ系で有名なのは下記の5つ。
・Serum
・Spire
・VPS Avenger
・MASSIVE
・SubLab XL
Serum~MASSIVEは、この中からどれか1つ持っていれば何とかなります。
(工夫次第で近い音は出る)
Serum
身の回りで一番ユーザーが多いシンセ。
とりあえず迷ったらコレ。
分かりやすいUIで、いろいろできる万能シンセ。
プリセット数もとても多い。
今どきの音楽全般で使う事ができます。
もし今、1つしかシンセを所有できないとしたらSERUMが第一候補(持って無いので詳細は不明)
Spire
音が太い事ことが強み。
工夫次第でいろいろできますが… EDM、トランス、ハードコアが主な用途。
私がNhatoさんに憧れて1番最初に買ったシンセ。
ただ、ビンテージ系の音が好きだと分かったので最近はあまり使ってない。
けど、良いシンセの1つとしておすすめできます。
私に合って無かっただけ。
VPS Avenger
最近注目されてるシンセ。
ユーザーは少なく、情報やプリセットは少ない。
だが、使ってる人の評価は高い印象。
私も持って無いので詳しい事は分かりませんが… 良さそうなので紹介。
MASSIVE
KOMPLETE 14というプラグインのハッピーセットを買うとついてくるシンセ。
個人的な感想、正直わざわざこれを買う理由はあまりないが…
1つ特殊なつよみがあります。
それが、SleepFreaksの解説記事や動画で使われてる事。
SleepFreaksは初心者でもわかりやすい有名な音楽解説系メディア。
ここを参考にしたい方、初心者で何も持って無いから「KOMPLETE 14」を買うという方におすすめ。
まとめると、初心者、初めて使う人向け。
上級者になっても使えるスターターセットというイメージ。
SubLab XL
これはサブベースを作るのに特化したシンセサイザーです。
各方面で評価が高く、私も実際持っていて、使って良いと感じてるので紹介。
ただ、1本目の万能型シンセで持つものではないです。
ビンテージシンセ(ポリフォニック)
1980~1990年代の音を再現するのに向いたシンセを紹介します。
Synth 1
1995年登場の「Clavia NORD LEAD2」をお手本に作られたシンセ。
無料でアナログシンセっぽい音が出せる。
普通に初心者の方が、入門機として使うのにアリな選択肢の1つ。
JD-800
1990年代に活躍した、日本製のポリフォニックシンセ。
「歴史を調べる」の章で紹介した90年代、小室哲哉系の音が出るシンセ。

これのプリセット53番「TK – Piano」がとても有名。
90年代のJ-POPで聞いたことのあるような音になります。
このシンセはRoland cloudのフリープランに加入後、JD-800を単品で買うことができます。(149$)
…ただ、CPU使用率が高い、重いなどの評判もあり。

Roland cloud製品。
JD-800と909Drum Machineは買う価値あり。
RePro-5
1970~1980年代前期に「Prophet-5」というシンセが流行りました。
「歴史を調べる」の章で紹介した70~80年代、YMO系の音が出るシンセ。
これの再現シンセのおすすめがRe-Pro。
ソフトでは、Re-Proが一番いい音と言われています。(その分重い)
負荷を気にする人は「Prophet-5 V」という選択肢もアリ。
ただ、Reproの方が評価が高い。
Polymode / Poly M
これも1970~1980年代前期系で紹介。
Moogという1960年から続く老舗メーカーがあります。
そこが出したポリフォニックシンセが「Polymoog」です。
これの再現ソフト「Polymode」や「PolyM」です。
Moogは歴史が古く、ファンの多いメーカーなのでこちらもおすすめ。
OB-E or Eight Voice
もう1つ、1970~1980年代前期系を紹介。
OBERHEIM SEMという小さなシンセを8個並べた「8 Voice」というシンセが出ました。
これも、ややコアなモノですが… 一定のファンがいる機種なので紹介。
8 VOICEの再現シンセでおすすめなのが下記の2つ。
・OB - E
・Eight VoiceOB – Eは、元の8 Voice制作者の協力を得ています。
が、少しお高い。
Eight VoiceはCherry Audioのシンセ。
Cherry Audio感がやや入りますが、安価で使えます。
こちらもおすすめ。

通称モンスターマシーンと呼ばれるシンセ。
持って無いが、前から興味があって”ほしい”と思っている。
ただ、私の中で”必要”までは行かなかった。(Re-Proあるので)
◆1970年~1980年前期系のシンセについて
Q、Prophet-5や、Polymoogも含め、いったいどれを選べばいいか?
A、もう、このあたりはメーカーの好みの域。見た目で選んでいいレベル。
細かい事を気にしないなら「Prophet-5」「Polymoog」「8voice」の中から
どれか1つ持っていれば、ビンテージ系は何とかなる。Dexed
これは1980年代前期の音。
YAMAHAから出た、FM音源のシンセ「DX7」が当時大流行しました。
FM音源 = 雑に紹介すると、金属っぽい音が得意なシンセ当時画期的だったFM方式は、これまで出せなかった音が出せると注目されてました。
初音ミクのデザイン元ネタになるぐらい影響力があったシンセ。
これの再現シンセでおすすめなのが「Dexed」です。
無料で、多くの人にはこれで十分。
他にもDX7を再現した「Dx7 Ⅴ」や、FM音源の進化系「FM8」などが出ています。
(これは、コアなオタク向け)
用途としては、1980代前半の音を出す、初音ミクリスペクトで使うなどが考えられます。
ただ今はFM方式は廃れぎみなので… わざわざ使うものではないです。

変わり種の飛び道具で使うにはアリですが…
よくあるシンセのルールから、大きく外れるので学習コスト高め。
CMI-Ⅴ
1980年代後期のポリフォニックシンセは何処へ…?
思われそうなので、その頃のシンセを1つだけ紹介だけします。(おすすめはしません)
◆1980年後期の雑紹介
→ FM方式でいろんな音が出せる!
→ やっぱ楽器などは無理!
→ そして、「楽器などは録音した音を記録して使おう」
…となりました。1980年代後期、PCMという今でいうサンプリング音源が流行りました。
その中で、比較的有名なのが「Fairlight CMI」というシンセ。
これのソフト再現が「CMI-Ⅴ」です。
確かに面白いですが…
これはマニアックすぎるのでコアな歴史オタク以外買うものではない。
もっと他のシンセを揃えた方が良い。
どうしても1980年後期の音が欲しい方だけ、このシンセを検討してください。

悪くはないし、面白い音が出ますが…
用途が特化しすぎている。
80年代サンプルパックを買った方が安くて色々解決しそう。
ビンテージシンセ(モノフォニック)
1960~1970年代のシンセです。
この頃は和音が出ませんでした。
今ではモノフォニック自体、あまり使うことがありませんが…
このあたりを再現するのにおすすめなシンセも紹介します。
ARP2600 V / CA 2600
セミモジュラーのモノフォニックシンセ。
ガンダムやスターウォーズの効果音製作に使われた名機「ARP 2600」があります。
これの再現シンセが「ARP 2600 Ⅴ」と「CA 2600」です。
CA 2600を持ってる人間の感想ですが…
明るく強い音が出ます。
先ほど紹介したシンセより、
より深いビンテージ感がある音を出したい方におすすめ。
Mini Ⅴ / Minivers
Moog社が出したモノフォニックシンセが「Mini Moog」です。
これの再現シンセが「Mini Ⅴ」や「Minivers」です。
正直、Polymoogの再現の方が使いやすいですが…
Moog系のより古い音を出したい方はこちらも検討してください。
Voltage ModularのVM2500
さらに歴史が古くなります。
1960年代は線を繫いで音を出すモジュラー形式が主流でした。
その時のARP 2500を再現したのがVM2500。
これはVoltage Modularというモジュラーシンセの拡張機能として用意されてます。
初心者にはおすすめできません。
が、コアなモジュラー使いを目指す方にはおすすめ。
Voltage ModularのVM900
VM 900はMoog系のモジュラーシンセの再現です。
こちらもVoltage Modularというモジュラーシンセの拡張機能として用意されてます。
1960年代の太古のMoogサウンド。
初期のYMOの音を出したい方や、コアなモジュラー使いを目指す方におすすめ。
まとめ
今回はシンセサイザーの選び方について紹介しました。
・同じ処理でもそれぞれ違う音が出る
・思った音を出すには、その思った音について掘り下げる
・掘り下げ方は歴史を調べたり、参考にしてる人を調べる事でてきる
・あとは、自分の用途を考えてシンセを選ぶ
その上であえておすすめを紹介するなら下記。
・今どき系シンセならSERUMがおすすめ
・1990年代ならJD-800
・それ以降の、ビンテージシンセ系ならRe-Pro5 …がおすすめ
また、他にも音楽について解説しています。
ぜひ、こちらもご覧ください。


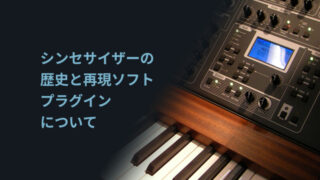
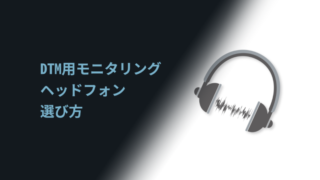



コメント